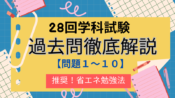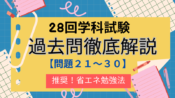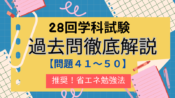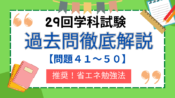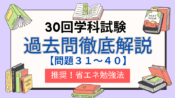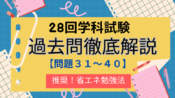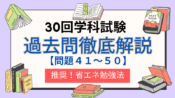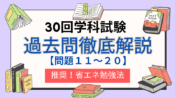《国家資格第28回》学科試験 過去問解説〔問題11~20〕

問題11 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | ○ | × |
1)エゴグラムは交流分析のバーンの弟子、デュセイが開発したものであり、エリスの論理療法とは別。よって誤り
2)ゲシュタルト療法を提唱したのはパールズであり、デュセイではない。代表的な技法には「エンプティチェア」がある。よって誤り。
3)設問のとおり。ロゴセラピーはフランクルが創始し、「生の意味」を見出すことを支援する心理療法である。
4)吉本伊信は内観療法を創始。論理療法はエリスが創始した。よって誤り。
問題12 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | × | ○ | ○ |
1)設問のとおり。交流分析はアメリカの精神科医エリック・バーンによって開発された心理療法。
2)「エニアグラム(エニアグラムは人の思考や行動パターンを9つのタイプに分類するもの)」ではなく「エゴグラム」の誤り。エゴグラムは、3つの自我状態(親・大人・子ども)へのエネルギーの分布をグラフ化するもので、バーンの弟子・デュセイが開発。よって誤り。
3)設問のとおり。交流分析には、構造分析・交流パターン分析・ゲーム分析・脚本分析の4つの分析があり、交流パターン分析では、相補的交流・交差的交流・裏面的交流に分類される。
4)設問のとおり。「ストローク」とは、人と人との間で交わされる心のふれあい。肯定的(陽性)・否定的(陰性)の両方がある。
問題13 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | ○ | ○ | × |
1)設問のとおり。社内検定認定制度は、厚生労働大臣が認定する制度である。
2)設問のとおり。キャリア形成・リスキリング推進事業では、全国のハローワークに専用の相談コーナーが設置されている。
3)設問のとおり。教育訓練給付制度の対象講座を検索できるシステムであり、内容も適切。
4)「キャリコンサーチ」は、国家資格キャリアコンサルタントと企業・個人をつなぐマッチング支援システムであり、設問の内容とは異なる。よって誤り。
問題14 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | × | × | × |
1)設問のとおり。キャリアコンサルティングを行うしくみがある事業所の割合は、正社員では41.6%、正社員以外では24.7%である。
2)「キャリアコンサルティングをしていく上で問題がある」という事業所は、正社員対象で73.6%、正社員以外対象で65.3%と、どちらも50%を上回っている。よって誤り。
3)ジョブ・カードについて、「内容を含めて知っており活用している」割合はわずか1.2%。よって誤り。
4)主体的なキャリア形成に向けた取り組みのうち、「キャリアコンサルティングの実施」は12.7%にとどまっている。最も多いのは「上司による定期的な面談の実施」(1on1等)で、65.8%。よって誤り。
問題15 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 |
1)設問のとおり。教育訓練給付金は、指定された講座を修了した場合に受講費用の一部が支給される制度で、キャリア形成や就職支援が目的。
2)在職中の被保険者だけでなく、離職後1年以内など一定条件を満たせば離職者も対象になる。よって誤り。
3)設問のとおり。教育訓練給付金には「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類があり、いずれも正しい分類。
4)設問のとおり。専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の受給には、訓練前キャリアコンサルティングの受講が必要。
問題16 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | × | 〇 |
1)「職業訓練受講給付金」を一定の要件のもとで受けられるのは、雇用保険を受給できない人を対象とした「求職者支援訓練」。よって誤り。
2)雇用保険を受給しながら訓練を受けるのは「離職者訓練」であり、「求職者支援訓練」ではない。よって誤り。
3)「求職者支援訓練」は、民間教育訓練機関が厚生労働省の認定を受けて実施している。よって誤り。
4)設問のとおり。
問題17 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
厚生労働省「公正な採用選考の基本」
2)設問のとおり。住宅状況(借家・持ち家など)に関する情報も、選考時には配慮が必要な項目。
3)設問のとおり。現住所の略図なども、本人の資質とは関係のない情報として、配慮が求められる。
4)「自覚している性格」は、本人の職務適性に関する判断材料となるため、選考時に配慮すべき項目には該当しない。 よって誤り。
問題18 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | × | × | × |
1)設問のとおり。企業が求めるスキルと現有社員のスキルとのギャップを埋めることは、人材開発の基本的な役割の一つ。
2)OJTは実践的な学習が可能な反面、指導者の力量やモチベーションによって成果に差が出やすいというデメリットがある。よって誤り。
3)個別対応のキャリア開発の重要性は高まっているが、特定の層(経営幹部、管理職、専門職)に重点を置いているとは限らない。よって誤り。
4)CDP(キャリア開発プログラム)は、Off-JTだけに限定されるものではなく、研修や配属などを含めた包括的・長期的な育成の仕組みである。よって誤り。
問題19 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
副業・兼業の促進に関するガイドライン
1)設問のとおり。副業・兼業を行う労働者に対しても、使用者には労働契約法第5条に基づく安全配慮義務がある。
2)設問のとおり。労働者には秘密保持義務があり、業務上の秘密が漏洩するおそれがある場合は、副業・兼業を制限することができる。
3)設問のとおり。労働者には競業避止義務があり、自社の利益を害する副業・兼業については制限の対象となりうる。
4)「程度・態様に関わらず」すべての副業・兼業が就業規則違反に当たるわけではない。
形式的に規定に抵触していても、職場秩序や労務提供に支障がないと判断される場合、懲戒処分は認められない。よって誤り。
問題20 難易度:難
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | 〇 | × | × |
1)自営業主・家族従業者の数は、2013年の729万人から2023年の639万人へと減少している。よって誤り。
2)設問のとおり。女性雇用者に占める非正規雇用者の割合は、2013年の55.8%から2023年には53.2%に低下したものの、依然として5割を超えている。
3)65歳以上の高齢者の就業率は、2013年の20.1%から2023年には25.2%へと上昇している。よって誤り。
4)無期契約と有期契約の雇用者数はいずれも増加しており、無期契約は13万人、有期契約は14万人の増加。よって誤り。
>>問題21~30へ