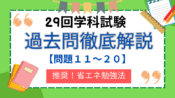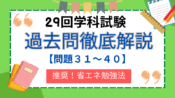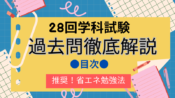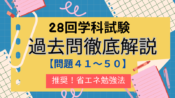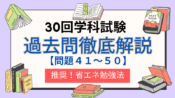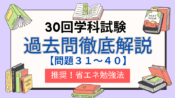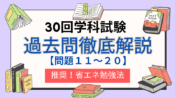《国家資格第29回》学科試験 過去問解説〔問題21~30〕
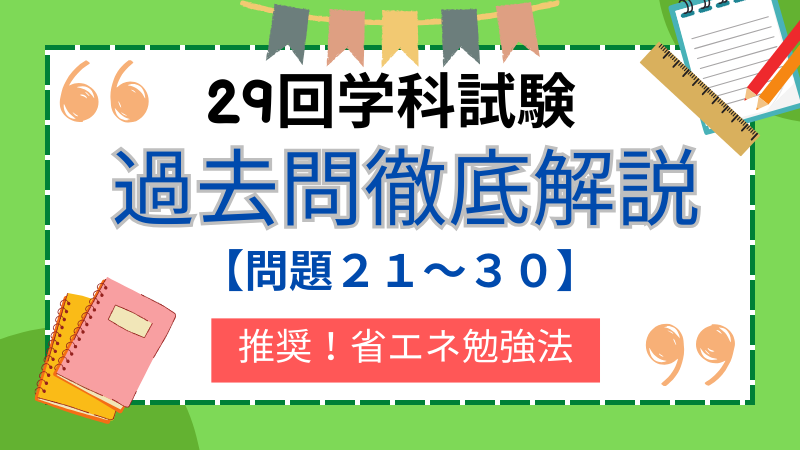
問題21 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | × | × | × |
1)設問のとおり。就業していない層は、①就業希望のない無業者、②求職活動はしていないが就業希望がある無業者、③求職者に分類され、最も人数が多いのは①就業希望のない無業者(在学者を除く)である。
2)「男女」ではなく「女性」が該当する。59歳以下の女性の約4割が「出産・育児・介護・看護・家事のため」を就業希望がない理由としているが、男性は割合が低い。よって誤り。
3)就業希望はあるが求職活動をしていない無業者の、求職活動を行っていない理由として最も多いのは、男性は「病気・けが・高齢のため」であり、59歳以下の女性は「出産・育児・介護・看護のため」である。よって誤り。
4)逆である。就業希望はあるが求職していない無業者は、男女とも「60~69歳」よりも「59歳以下」の方が多い。よって誤り。
問題22 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | × | ○ | ○ |
1)設問のとおり。令和4年の改正により、育児休業を取得しやすくするための雇用環境整備、個別の周知や意向確認の措置が義務化された。
2)有期雇用労働者に関する「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃され、取得要件は「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」場合のみとなった。よって誤り。
3)設問のとおり。令和4年の改正で、出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」が取得可能となった。
4)設問のとおり。令和4年の改正により、原則として子が1歳 (最長2歳)まで、分割して2回取得可能となった。
問題23 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | ○ | × | × |
1)支持政党に関しては、本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)であり、就職差別につながるおそれがあり、採用選考時に配慮すべき事項である。よって誤り。
2)設問のとおり。例示された課題を用いて本人の問題解決能力を問うことは、公正な採用選考に反しない。
3)求人内容の説明や情報提供で男女差を設けることは、性別を理由とする差別に該当する。よって誤り。
4))合理的理由なく身長・体重・体力を要件とすることは、間接差別にあたり、禁止されている。よって誤り。
問題24 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | × | × | × |
1)設問のとおり。労働基準法第38条では、事業場が異なっても労働時間は通算する規定がある。
2)労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要がある。よって誤り。
3)36協定の対象者は「労働者」であり、雇用形態を問わず該当するが、管理監督者など使用者とみなされる者は対象外である。よって誤り。
4)休日は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならず、ある特定の4週間のなかの任意の4日について休日を与える方法は認められる。よって誤り。
問題25 難易度:難
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
1)設問のとおり。派遣労働者の待遇は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」により確保することが義務化されている。
2)設問のとおり。同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合、派遣元事業主が第二人事部的に位置付けられ、労働市場における需給調整機能が果たされなくなることから、総労働時間の8割以下に制限されている。
3)設問のとおり。派遣先は、離職後1年以内の元社員を派遣労働者として受け入れることができない。ただし、60歳以上の定年退職者は例外である。
4)通常の人材派遣においては、労働者派遣に先立って面接をしたり、書類選考をしたりすることは、派遣労働者の特定を目的とする行為として禁止される。よって誤り。
問題26 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | × | ○ | ○ |
小学校学習指導要綱 中学校学習指導要領 高等学校学習指導要綱
1)設問のとおり。
2)社会情緒的能力は「学びに向かう力・人間性」と無関係とはいえないが、言葉として示されいない。よって誤り。
3)設問のとおり。
4)設問のとおり。
問題27 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | × | 〇 |
1)設問のとおり。職業レディネス・テストの実施効果として、生徒自身が自分の興味や自信度を知る手がかりとなる。
2)設問のとおり。検査により様々な職業を知るきっかけになる点も、期待される効果として適切である。
3)検査には限界があり、結果に基づいて教員が生徒を特定の方向へ誘導するような支援は不適切である。よって誤り。
4)設問のとおり。グループワークによる振り返りやフィードバックの実施は、検査結果をより深く理解し活用する方法として適切である。
問題28 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | × | ○ | ○ |
1)設問のとおり。高等教育機関への進学率は84.0%で、前年度より0.2ポイント上昇し、過去最高であった。
2)専門学校進学率は21.9%で、前年度より0.6ポイント低下している。よって誤り。
3)設問のとおり。短期大学(本科)進学率は、平成6年の13.2%をピークに、令和5年には3.4%に低下している。
4)設問のとおり。大学(学部)進学率は57.7%で、前年度より1.1ポイント上昇し、過去最高であった。
問題29 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | × | 〇 |
1)設問のとおり。労働者が病気休業期間中に安心して療養に専念できるよう、これらの情報提供等の支援を行うことは適切である。
2)設問のとおり。職場復帰の判断が、診断書の内容だけでは不十分な場合、産業医等は労働者の同意を得た上で、必要な内容について主治医からの情報や意見を収集することになっている。
3)職場復帰は、社員自ら行うのではく、事業場内産業保健スタッフ等が中心となって判断を行う。よって誤り。
4)設問のとおり。
問題30 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
1)設問のとおり。発達障害者の特性を活かしやすい職務を提供したり、作業を工夫して職務を創出することは適切な支援である。
2)設問のとおり。発達障害者の定着や職場適応を促すため、ジョブコーチによる人的支援を活用することは適切である。
3)設問のとおり。感覚過敏の人に対しては、サングラスや耳栓・ヘッドフォンの使用を認める、衝立を用意して周囲と遮断された空間を用意する等の配慮を行っている事例がある。
4)本人が非難されたと感じるほど、強い口調や大きな声ではっきりと注意することは適切ではない。よって誤り。
>>問題31~40へ