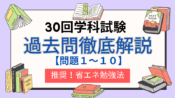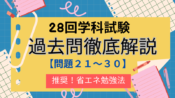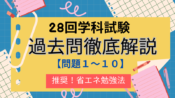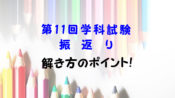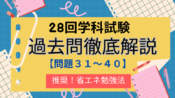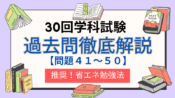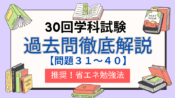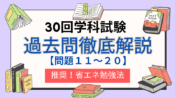《国家資格第30回》学科試験 過去問解説〔問題11~20〕
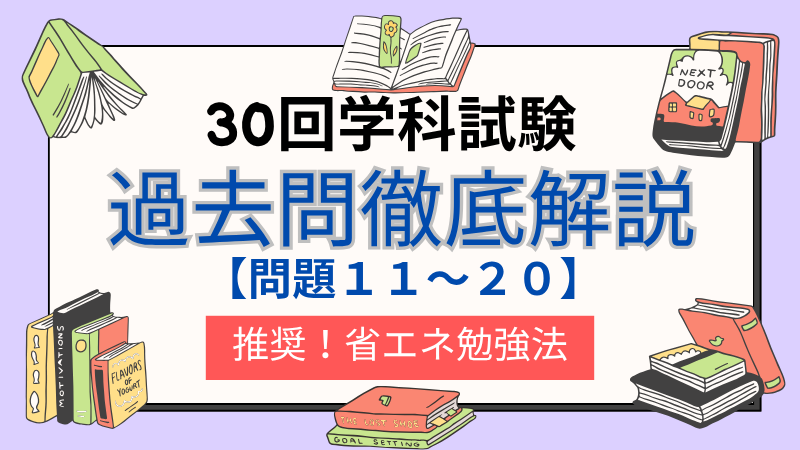
問題11 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | ○ | × | × |
1)ハロートレーニングは失業者だけでなく、在職者向けや学卒者向けの訓練もある。離職者訓練以外にも在職者訓練・学卒者訓練・障害者訓練がある。よって誤り。
2)設問のとおり。ハロートレーニングでは、介護・簿記・パソコン・医療事務・電気工事士・ITなど、資格取得を目指す多様なコースが実施されている。
3)最長1年とは限らない。例えば離職者訓練の期間は概ね3か月から2年である。よって誤り。
4)離職者訓練や求職者支援訓練は、テキスト代等は本人が負担する。また、在職者訓練や学卒者訓練は有料。よって誤り。
問題12 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | ○ | × | ○ |
1)設問のとおり。OFF-JTを実施した対象を職層等別にみると、正社員では「新入社員」が58.9%で最も多く、「中堅社員」が 56.9%、「管理職層」が 48.0%となっており、「正社員以外」は 28.3%となった。
2)設問のとおり。計画的なOJTは、正社員、正社員以外ともに、おおむね規模が大きくなるほど実施率は高くなる傾向がある。
3)能力開発上の問題点で最も多いのは「指導する人材が不足している」である。よって誤り。
4)設問のとおり。「人材開発支援助成金を利用した」と回答した事業所は9.8%。この内容は令和5年度版のみに記載されている内容。
問題13 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | × | ○ |
1)これらの留意点は、労働者を雇用する場合に発生するものであり、労働者が個人事業主として副業・兼業を行う場合には原則該当しない。よって誤り。
2)就業時間の把握・ 管理や健康管理への対応が必要で、使用者は確認を行う必要がある。他にも職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応もある。よって誤り。
3)労働者が副業・兼業を通じて社内では得られない知識やスキルを獲得し、自律性を高められる点は企業側の「メリット」であり、「留意点」として指摘はされていない。よって誤り。
4)設問のとおり。労働者のメリットとして、本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができることが挙げられる。
問題14 難易度:難
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | ○ | × | ○ |
1)設問のとおり。職業能力評価基準の定義として適切である。
2)設問のとおり。人材育成、採用、人事評価など企業の人事管理の基準として活用され、自社の実情に合わせてカスタマイズすることも可能。
3)「次のレベルに上がるには何が不足してるのか」、「自分(または部下)の能力レベルはどの程度なのか」を把握できるのは、職業能力評価シートである。よって誤り。
4)設問のとおり。
問題15 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | × | × | × |
1)設問のとおり。職場改善に積極的な企業の残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢などの職場情報を検索・比較できるWebサイトである。「ダウンロード」については、掲載中の職場情報のCSVファイルや、各企業の一般事業主行動計画のPDF等がダウンロードできる。
2)若者雇用促進総合サイト、女性の活躍推進企業データベース、両立支援のひろばに散在していた情報を一元的に閲覧できるようにしたのが「しょくばらぼ」である。よって誤り。
3)企業の残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢などの職場情報を掲載するサイトであり、求人情報が掲載されているわけではない。よって誤り。
4)しょくばらぼ自体には求人情報はないが、「ハローワークインターネットサービス」や「職業情報提供サイト(jobtag)」と連携している。よって誤り。
問題16 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | 〇 | × | × |
参考:令和6年働く女性の実情
1)誤り
2)設問のとおり
3)誤り
4)誤り
問題17 難易度:難
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | 〇 | × |
1)日本の就業率(15~64歳)について、2005年以降の推移をみると、おおむね上昇傾向にある。よって誤り。
2)65歳以上男性の労働力率はアジア地域が欧米より高く、韓国(48.0%)は日本(34.9%)を上回っている。よって誤り。
3)設問のとおり。65歳以上男性の労働力率は、アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツでは大幅に上昇しているが、日本では1985年37.0%から2022年34.9%へわずかに低下している。
4)2022年の日本の就業率(男女計)は78.4%で、ドイツ(76.9%)、イギリス(75.5%)と同水準。アメリカ(71.3%)やフランス(68.1%)を上回る。 よって誤り。
問題18 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | ○ | × | × |
1)就業率は男女計では約6割で、男女別にみると、男性は約7割、女性は約5割となっている。よって誤り。
2)設問のとおり。女性の非労働力人口のうち、就業希望者は約160万人で、完全失業者の2.2倍に相当する。多くの女性が働く意欲はあるが求職活動には至っていない状況である。
3)正規雇用労働者数については、女性を中心に2015年から2023年まで9年連続で増加している。よって誤り。
4)非正規雇用労働者は、2020年と2021年には感染症の拡大による景気後退の影響から一時的に減少がみられたものの、長期的には男女ともに増加傾向である。よって誤り。
問題19 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | 〇 | × | × |
1)労働力人口は、全人口ではなく、「15 歳以上」の人口に占める労働力人口の割合である。よって誤り。
2)設問のとおり。完全失業率の定義として適切である。なお、労働力人口とは、15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたものである。
3)完全失業者は、①仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった。②仕事があればすぐ就くことができる。③調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた。の3つの条件を満たす者である。よって誤り。
4)非労働力人口とは、15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者と定義づけられている。具体的には専ら通学、家事をしている人、その他(高齢者など)が該当する。よって誤り。
問題20 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
パートタイム・有期雇用労働法の概要
1)設問のとおり。事業主はパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは(労働契約の更新時を含む)、事業主は実施する雇用管理の改善に関する措置の内容を説明することが義務付けられている。
2)設問のとおり。求めがあった際には説明義務がある。
3)設問のとおり。パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制(苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制)を整備することが義務付けられている。
4)すべての事業所に義務づけられているのではなく、事業所ごとに選任することを「努力義務」としている。よって誤り。
>>問題21~30へ