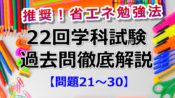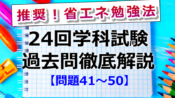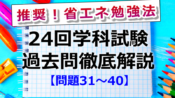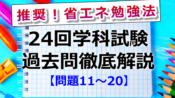《国家資格第23回》学科試験 過去問解説〔問題11~20〕
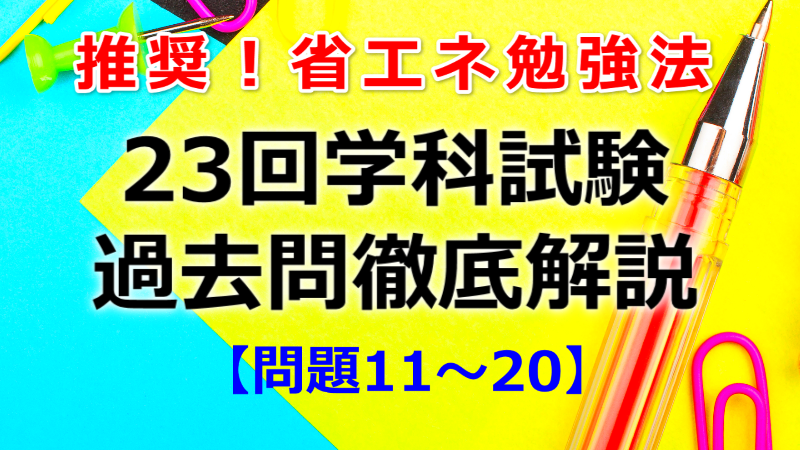
問題11 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | ○ | ○ | × |
1)設問のとおり。社会全体のDXが加速化しており、あらゆる産業分野におけるITの利活用ができる人材(IT利活用人材)のニーズの高まりを見据えて、全ての働く方々に必要とされるITリテラシーの付与を推進する必要がある。
2)設問のとおり。労働者は、日々の業務を通じて職業能力の向上を図るとともに、企業任せにするのではなく、若年期から自身の職業能力開発の必要性を継続的に意識しながら、時代のニーズに即したリスキリングやスキルアップを図っていく必要がある。
3)設問のとおり。技能検定等の職業能力評価制度や職業情報提供サイト(日本版O-NET)については、それぞれの職業に必要な能力の把握や能力の客観的な評価に活用できるものであり、労働者のキャリア開発の目標設定・動機付けとして機能することにより、労働者の主体的な能力の向上にも資するものである。
4)職業能力開発を進めるにあたり、企業の役割は依然として重要である。よって誤り。
問題12 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | ○ | × | × |
1)ミドルシニア層のホワイトカラー職種の人がキャリアチェンジ、キャリア形成を進める際に活用することを想定している。。よって誤り。
2)設問のとおり。「ポータブルスキル」とは、職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルのことである。
3)ポータブルスキルの要素は大きく分けると、「仕事の仕方」と「人との関わり方」がある。よって誤り。
4)相談者の専門能力や興味・価値観などを踏まえた診断ではないため、想定していなかった職務・職位が提示される可能性がある。よって誤り。
問題13 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | ○ | ○ | × |
1)設問のとおり。
2)設問のとおり。
3)設問のとおり。
4)キャリアコンサルタントの主な役割は、クライアントが自らのキャリアを理解し、今後の方向性やキャリアの選択を自分で決められるようにサポートすること。具体的な昇進、配置転換、処遇などの人事判断や行動は企業の人事部門や経営陣の責務である。よって誤り。
問題14 難易度:難
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ○ | ○ | ○ | × |
人材開発支援助成金には7つのコースがあり「人への投資促進コース」は令和4年~8年度の期間限定助成であり、下記5つの訓練への助成をしている。
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練(大学や大学院での訓練も含む)ー選択肢1
・情報技術分野認定実習併用職業訓練(IT分野未経験者の即戦力化)
・長期教育訓練休暇等制度(長期休暇や短時間勤務等制度の導入)ー選択肢3
・自発的職業能力開発訓練(従業員の自発的な受講への事業主への助成)
・定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)ー選択肢2
よって、選択肢4が対象ではない。
問題15 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 |
「CDP(career development program)」は、従業員のキャリアの成長と発展を支援するための体系的な取り組みを示している。企業は、CDPを通じて従業員のモチベーションを高め、リテンション(定着率)を向上させ、組織のパフォーマンスを最適化することを目指す。
1)設問のとおり。
2)労働者の意向や希望を尊重することは必須である。よって誤り。
3)設問のとおり。
4)設問のとおり。
問題16 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | × | 〇 | 〇 |
1)設問のとおり。一定数以上の従業員を持つ事業主は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を「法定雇用率」以上の割合で雇用することが義務付けられている。
2)年齢制限が認められる場合もある。よって誤り。
3)設問のとおり。採用選考時に、就職差別を避けるためには「本人の責任ではない事項の取得」に注意が必要で、例として本籍や出生地、家族の情報、住宅の状態などの情報を避けるべきである。
4)設問のとおり。外国人を採用する際には、その人が就労予定の職種が在留資格の許可範囲内であるかや、在留期間の有効性を確認する必要がある。この確認は、在留カードやパスポートに記載された上陸許可証印、または外国人登録証明書(一定期間は在留カードとしても有効)を参照することで行える。
問題17 難易度:中
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | × | 〇 |
1)正社員に対して職業能力評価を行っている事業所 は50.2%であり、平成22年度調査から平成25年度調査までは60%台、平成26年度調査以 降は50%台で推移し、3年移動平均については、平成27年度調査以降では大きな変動はなかったが、直近では減少に転じている。よって誤り。
2)職業能力評価における検定・資格を利用している事業所は59.7%であり、利用していないとする事業所は39.8%である。よって誤り。
3)「人事考課の判断基準」が、活用方法として最も多い。次いで「人材配置の適正化」、「労働者に必要な能力開発の目標」である。よって誤り。
4)設問のとおり。職業能力評価を行っている事業所のうち、職業能力評価に係る取組の問題点の内訳は、「全部門・職種で公平な評価項目の設定が難しい」 (70.1%)が最も高い。
問題18 難易度:難
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | ○ | × | × |
1)実質GDPの成長率には大きな差がある。よって誤り。
2)設問のとおり。1990年から感染拡大前までの2019年までの累積で実質GDP は26%成長したが、時間当たり労働生産性の上昇と就業者数の増加が押上げに寄与する一方、一人当たり労働時間が押下げに大きく寄与し、就業者数と一人当たり労働時間を合わせた総労働時間の寄与はマイナスとなっている。
3)主要先進国は名目、実質賃金ともに安定して増加している。よって誤り。
4)2013年以降は、時給の増加によるプラス寄与が拡大していることが確認できるが、労働時間当たり実質GDPの伸びと比較すると、時給の伸びはこれまで十分とはいえず、時間当たり労働生産性の伸びと物価上昇率の合計に見合った時給や賃金上昇の実現に向けた取組が期待される。よって誤り。
問題19 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| × | × | 〇 | × |
1)専門職・技術職や非定型のサービス職の就業者シェアは上昇する一方、「生産工程・労務作業者」のシェアは一貫して低下するとともに、1990年代以降、販売職はやや低下しており、労働市場の二極化が進んでいる。説明が逆のため誤り。
2)転職入職率の推移をみると、男女別では、男性よりも女性の方が高い割合で推移している。説明が逆のため誤り。
3)設問のとおり。我が国では、勤続年数1年未満の雇用者の割合が国際的にみて低い一方で、勤続年数10年以上の雇用者の割合は、アメリカ、カナダ、イギリス、北欧諸国等と比較すると高く、イタリア、フランス等と同程度の水準となっている。
4)就業形態別に転職入職率、離職率をみると、いずれも一般労働者よりもパートタイム労働者の方が高い。説明が逆のため誤り。
問題20 難易度:易
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 〇 | 〇 | × | 〇 |
1)設問のとおり。労働力人口は、15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの。
2)設問のとおり。就業者は、従業者と休業者の総数を指す。また、家族従業者も、報酬を受け取っていなくても、労働をしていると考えられる。
3)完全失業者とは、以下の三つの条件を全て満たす人を指す。①調査期間中、一切働いていない(就業者でない)②仕事が提供されれば直ちに勤務することが可能 ③調査期間中に、求職活動や新しい事業の準備を進めていた(過去の求職活動の結果を待機中のケースも含む)。よって誤り。
4)設問のとおり。完全失業率とは、労働力人口に占める、完全失業者の割合である。
>>問題21~30へ
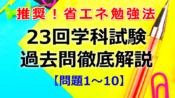
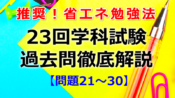
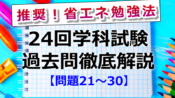
-3.jpg)